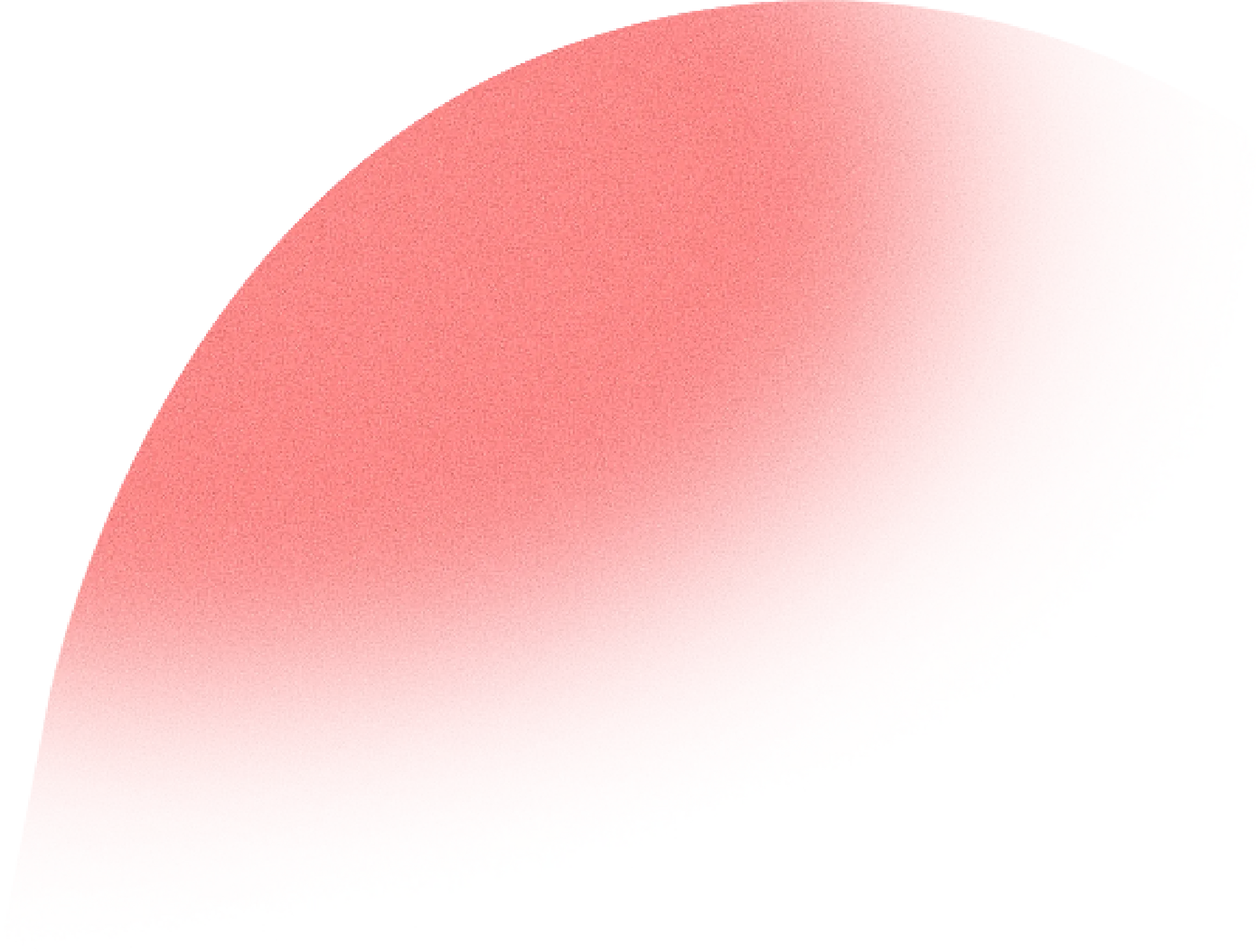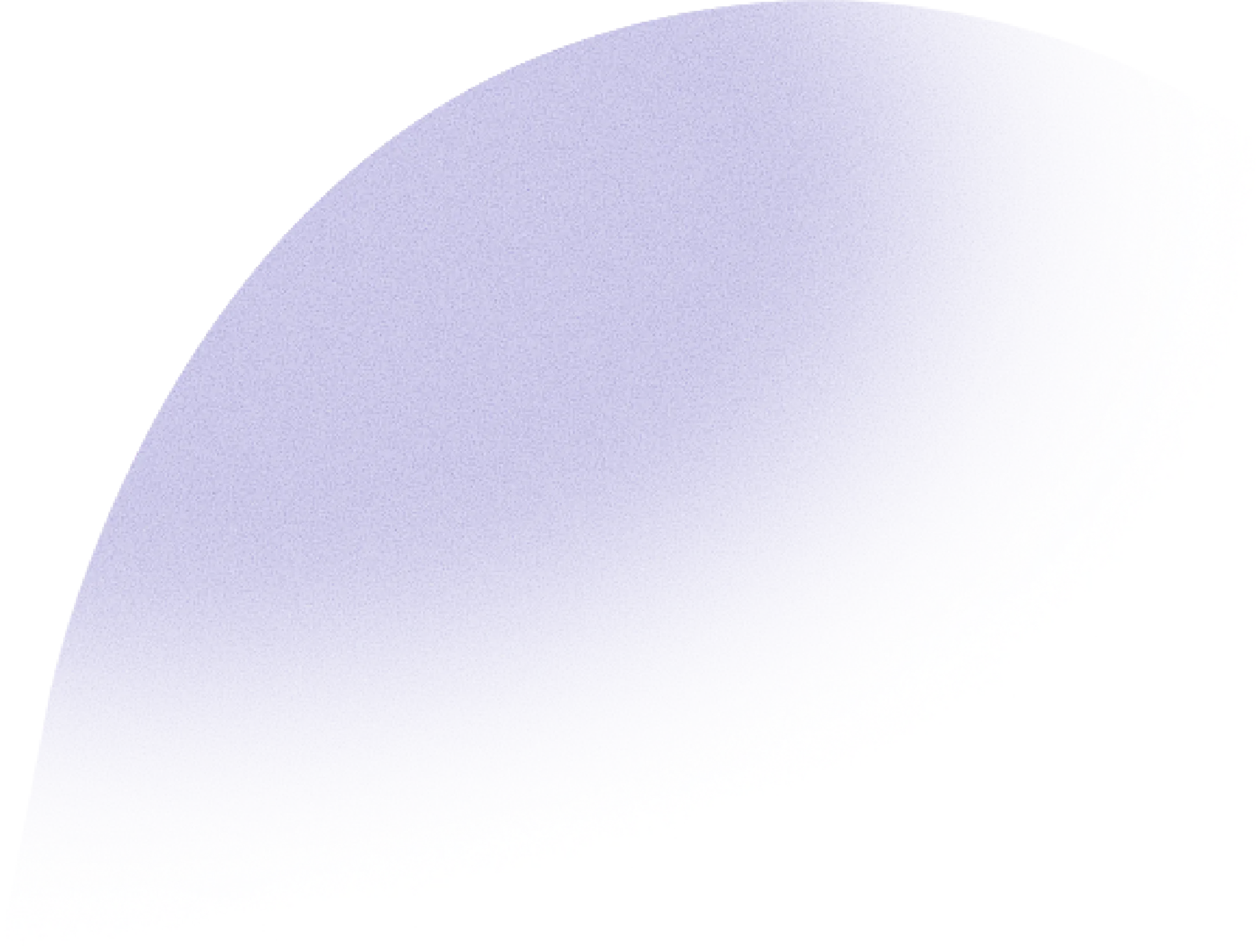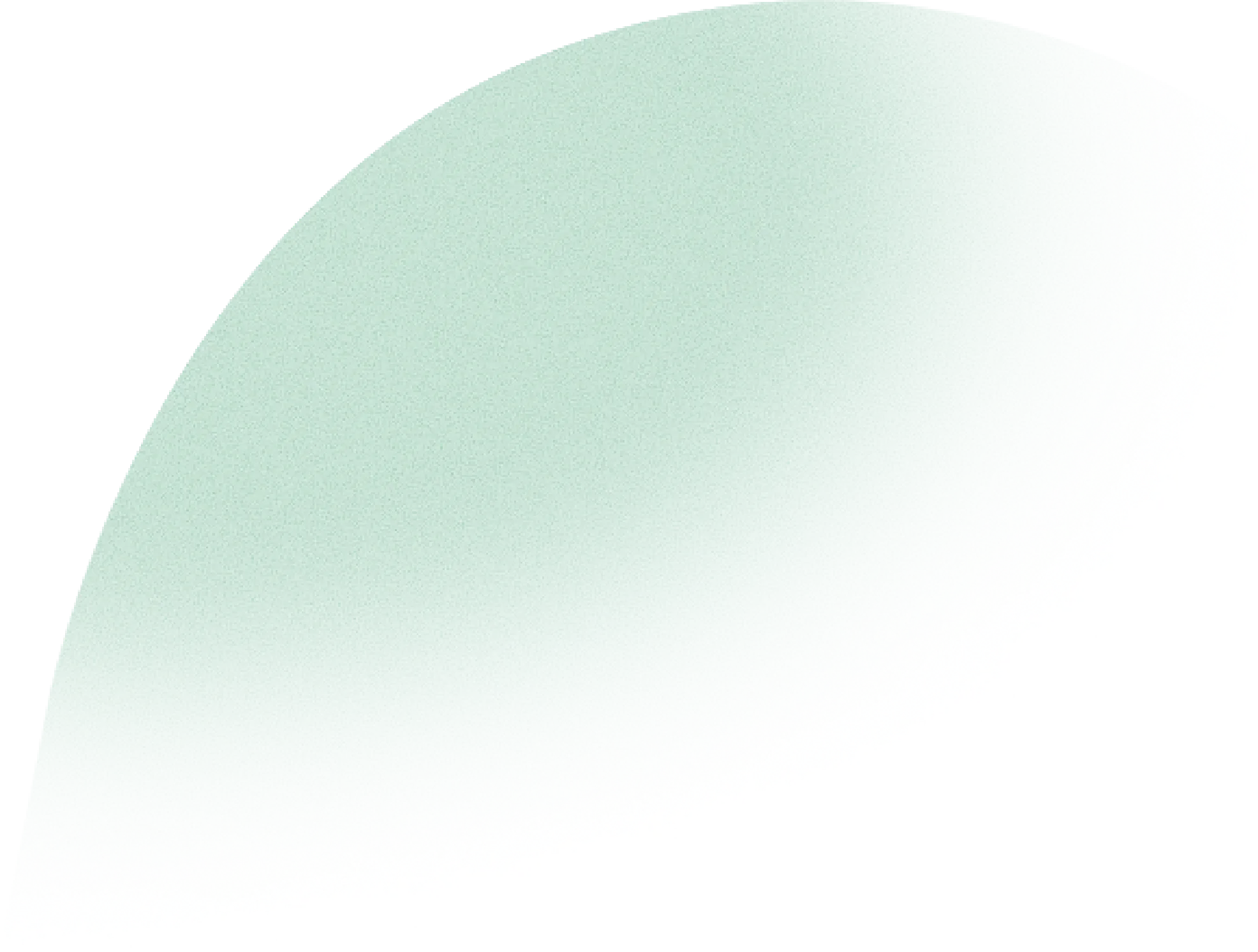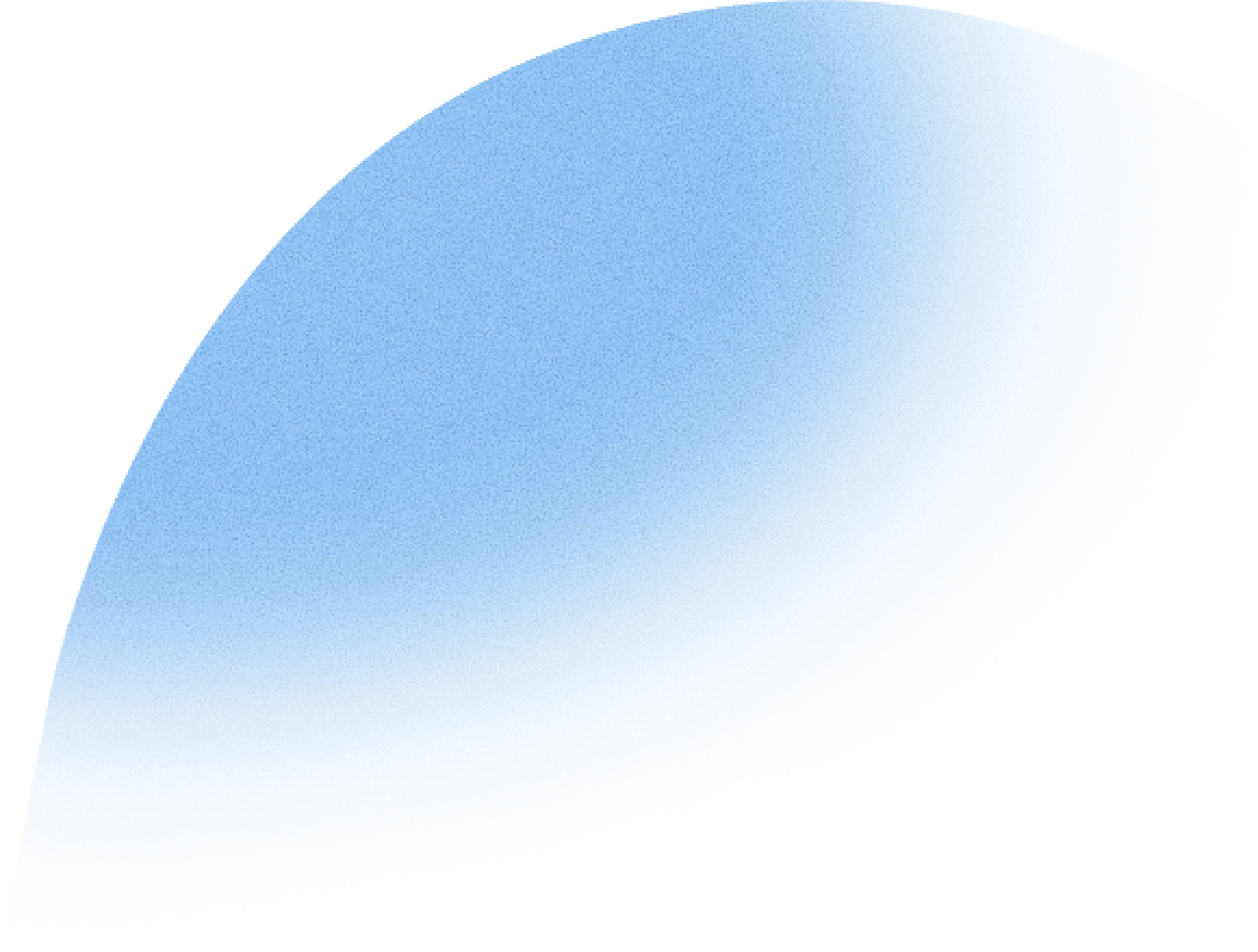日本の伝統美を象徴するものの一つが「婚礼衣装」です。特に和装の婚礼衣装は、時代とともに形を変えながらも、その根底にある意味や美意識は連綿と受け継がれてきました。白無垢、色打掛、黒引き振袖には、それぞれに深い歴史と意味が込められており、ただ「装う」ためのものではありません。
このコラムでは、和装の婚礼衣装における歴史を紐解きます。また、当学院の着付け教室では、きものを着る技術だけでなく、こうした文化や歴史についても学べる点もお伝えします。
1.平安時代から続く「白」の神聖性

和装婚礼衣装の原点ともいえるのが「白無垢」です。白無垢は、全身を白一色で統一した婚礼衣装で、神前式の際に花嫁が身にまとうもっとも格式の高い正礼装とされています。
「白」は、平安時代にはすでに神聖・清浄の象徴とされてきました。白無垢の「無垢」には「けがれのない」「純粋な」という意味があり、花嫁が生家の色を脱ぎ捨て、婚家の色に染まるという覚悟を表しています。
このような衣装が確立されたのは室町時代以降、武家社会の慣習に由来しますが、その精神性は今も変わりません。きもの一枚に込められた意味の深さにこそ、和装ならではの奥ゆかしさが宿っているのです。
2.江戸時代の華やぎ、色打掛の誕生
時代が下るにつれて、婚礼衣装にも華やかさが求められるようになりました。特に江戸時代になると、豪華絢爛な「色打掛」が登場し、花嫁衣装の中心的存在となります。
色打掛は、赤や金、黒など色とりどりの地に、鶴、松、梅、桜、鳳凰といった吉祥文様をあしらった打掛で、まるで絵巻物のように華やかな印象を与えます。結婚という慶びの場にふさわしい祝祭の装いとして、人々に愛されてきました。
素材には、重厚感のある緞子(どんす)や西陣織が使われ、織りや刺繍の技術は職人たちの粋の結晶といえるでしょう。色打掛は、婚礼の主役である花嫁を、まさに「舞台の主役」として際立たせる存在です。

3.凛とした美しさの象徴、黒引き振袖

一方、江戸時代後期から流行したのが「黒引き振袖」です。黒地に鮮やかな文様が映えるこのきものは、一般的な花嫁衣装として人気を集めました。
白無垢の清廉さとはまた異なる、黒には「誰にも染まらない」「強い決意」の意味があり、当時は白無垢や色打掛に次ぐ格式を備えていました 。
引き振袖とは、裾を長く引きずるように着るきもののことで、結婚式の場では、裾を引いて歩くその姿が、ゆったりとした所作を生み、優雅さを際立たせます。
現代でも、和装婚礼におけるお色直しや披露宴の衣装として用いられ、写真映えすることから人気が高まっています。帯や小物の合わせ方で個性を出しやすいのも、引き振袖ならではの魅力です。
4.男性の正装、紋付羽織袴の格式

和装婚礼は、花嫁だけでなく新郎の装いもまた格式を重んじます。男性の婚礼衣装として代表的なのが、「黒紋付羽織袴」です。
五つ紋の黒羽織と長着、仙台平の袴は、江戸時代に武士の正装として確立されました。家紋はその家のアイデンティティを示し、結婚という家と家の結びつきの場において、非常に重要な意味を持ちます。
花嫁の衣装が時代とともに多彩に変化する中で、男性の和装婚礼衣装は現在もその格式を守り続けています。和装婚礼は、夫婦としての門出を“衣”で整える、美しい文化の結晶なのです。
5.きものの意味を知ることで、魅力が膨らむ
きものは、日本人が千年以上にわたり育んできた文化です。中でも婚礼衣装は、人生の節目を彩る特別な一枚。「ただ美しい」だけではなく、「意味を知って着る」ことで魅力は何倍にも膨らみます。
また、きものは「着る」だけでなく「着付ける」文化でもあります。正しい所作、丁寧な扱い、美しく見える仕上げ方。それらすべては、知識と技術に裏打ちされたものです。
現代では、洋装が当たり前になり、きものを着る機会が少なくなりました。しかしだからこそ、改めて和装の価値を学ぶことができる場所。それが着付け教室です。
まとめ 伝統を「纏う」「着付ける」人になる学び場

当学院の着付け教室では、着付け技術だけでなく、歴史的背景から丁寧に学ぶことができます。所作の意味、素材や柄の選び方など、きもの文化を深く知ることができ、現代のスタイリングやブライダルシーンに活かせる知識が得られます。
実際に着付けを学ぶ中で、「婚礼衣装の着付け師として活躍したい」という新たな目標が生まれる方も多くいます。
もし、あなたが「きものを着てみたい」「和装婚礼の着付けに興味がある」と思ったなら、ぜひ一度、当学院の無料体験レッスンにお越し起こしください。
装いを超えた“日本の美”があなたを待っています!